五月人形には、鎧・兜・子供大将の3種類の内飾りと鯉のぼりなどの外飾りがあります。
5月人形
端午の節句のはじまりは奈良時代といわれます。
スポンサード リンク
スポンサード リンク
5月人形の由来
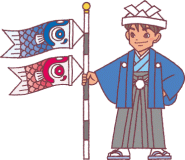 5月人形は、別名「武者人形」「5月雛(びな)」ともいって、昔からこれを5月5日の端午の節句に飾る習わしがあります。
5月人形は、別名「武者人形」「5月雛(びな)」ともいって、昔からこれを5月5日の端午の節句に飾る習わしがあります。
また5月5日は日本では古代から「薬日(くすりび)」とされ、厄除けをする習慣があります。これは611年5月5日、推古天皇が、奈良県の兎田野で鹿茸(ろくじょう・鹿の若い角)と薬草を採取する「薬狩り」を行なったという史実が日本書紀に残っていて、その後、薬狩りは恒例行事となり、この日を「薬日」としたといわれています。
菖蒲やよもぎなど、香りの強い薬草植物をお風呂にいれて入浴して、疫病や邪気を払いこどもの成長と健康を願うという風習が今日でも残っているのはご存じの通りです。
5月人形の起源ですが、鯉のぼりや武者絵を庭先に飾るという風習が江戸時代からあって、これを家の中で飾るようになったのが「武者人形」であるといわれます。
5月人形というと、鎧・兜や子供大将などの飾りを思い浮かべますが、こちらは子供の無事成長を願う「内飾り」、そして、立身出世を願う「鯉のぼり」は外飾りという位置づけにあります。
スポンサード リンク
内飾り、飾り棚について
5月人形の3段飾り棚を用いた「内飾り」の飾り方。
上段は、中央に鎧、兜などの具足一式、左右に弓矢立てと陣太刀立てを置きます。
またこの後ろに屏風か幔幕を張り、波に千鳥や鐘馗などを描いた旗指し物、のぼり、吹き流しなどを立てます。
中段は、中央に、陣笠、采配、軍扇を置き、その両側に、鐘馗や金太郎などの武者人形を飾ります。
下段は、三宝(さんぽう)に載せた菖蒲酒とちまき、柏餅を供え、左右に篝火を焚きます。
五月人形と言いますと、鎧・兜・子供大将の3種類の内飾りと、鯉のぼり・武者絵のぼり・鍾馗(しょうき)などの外飾りがあります。
人形店で五月人形の内飾りを購入する場合ですが、実はお店によって、鎧の得意なお店、兜が得意なお店、子供大将が得意なお店などがあるそうです。
やはり3種類の内飾りの中から1つを選ぶとすれば、鎧が選ばれるのではないでしょうか。
鎧と兜では、鎧の方がずっと高価であるイメージがありますが、同じ仕様だと、鎧は兜の1.2倍〜1.3倍位が目安だそうです。
鎧兜の選び方や注意点
鎧をお店で購入する場合ですが、五月人形は非常に価格帯に幅があってピンキリです。
お店では、大き目の高額商品の鎧、兜が飾ってあります。もちろん大きいものの方が立派に見えますが購入に当たっては飾る場所の広さ、スペースと予算を考えて選ぶ必要があります。
立派な和室がある場合は、段飾りや大き目の鎧飾りがいいでしょうが、マンション、アパート住まいの方は、ローボードの上に飾れるコンパクト飾り、収納タイプのものがいいでしょう。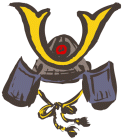
「5月人形を飾る時の注意事項」
・鎧兜の金属部分には直接触れず、手袋をする。
手の油や汗・ハンドクリーム等でが原因で、黒っぽく変色したシミが出てしまうことがありますので、必ず手袋をしましょう。
・箱に収納した状態や、飾り付けを完成させた状態をデジカメなどで撮っておくと、しまうときや次回の飾り付けの時に便利です。
・段飾りの場合は、上の段から飾っていく。手前から飾っていくと、後から飾るのにじゃまになりますし、引っかけたりしがちです。上から下、奥から手前の順に配置していきましょう。